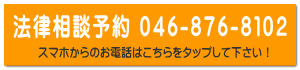横須賀の弁護士をお探しなら横須賀汐入法律事務所へ
取り扱い分野
①相続
②離婚関係
③成年後見等
④不動産トラブル
⑤借金問題
⑥損害賠償請求
⑦刑事事件
⑧その他
遺産分割
<相談例>
・遺産の分け方について,相続人間で話がまとまらない。
・法定相続人の一人が行方不明であるために,遺産分割の話し合いができない。
相続財産は相続人全員の共有と扱われるため(民法第898条),相続人が複数人である場合,誰が,どの遺産を引き継ぐのかを話し合って決めておかないと,例えば不動産を売却するためには,相続人全員の同意書を取り付けなければならない,というように煩雑な手続きを要することとなります。また,遺産分割協議をしないで放置してしまうと,次の相続が生じてしまう可能性もあるので,早めに遺産分割協議をした方が問題を拡げずに済むこともあります。
当事務所では,遺産の分割について相続人間で話し合いがまとまらない,話し合いができないという場合に,弁護士が代理人となって,ご希望に沿う遺産分割を目指します。
・遺産の分け方について,相続人間で話がまとまらない。
・法定相続人の一人が行方不明であるために,遺産分割の話し合いができない。
相続財産は相続人全員の共有と扱われるため(民法第898条),相続人が複数人である場合,誰が,どの遺産を引き継ぐのかを話し合って決めておかないと,例えば不動産を売却するためには,相続人全員の同意書を取り付けなければならない,というように煩雑な手続きを要することとなります。また,遺産分割協議をしないで放置してしまうと,次の相続が生じてしまう可能性もあるので,早めに遺産分割協議をした方が問題を拡げずに済むこともあります。
当事務所では,遺産の分割について相続人間で話し合いがまとまらない,話し合いができないという場合に,弁護士が代理人となって,ご希望に沿う遺産分割を目指します。
相続放棄
<相談例>
・被相続人に財産はなく,借金しかないので,相続したくない。
相続は,被相続人が死亡したのと同時に開始し(民法第882条),遺言書がなく,何も手続きを取らずにいると,法律で定められた相続人(法定相続人)が被相続人の遺産を相続したことになります(民法第920条)。そのため,上記相談例のように相続したくないような場合は,家庭裁判所に相続しない旨,すなわち相続放棄の申述をする必要があります(ただし,期間制限があります。)。
当事務所では,相続放棄に関する一般的なご説明のみならず,相続放棄するべきかどうかについても,具体的なお話をお聞きした上でアドバイスいたします。
・被相続人に財産はなく,借金しかないので,相続したくない。
相続は,被相続人が死亡したのと同時に開始し(民法第882条),遺言書がなく,何も手続きを取らずにいると,法律で定められた相続人(法定相続人)が被相続人の遺産を相続したことになります(民法第920条)。そのため,上記相談例のように相続したくないような場合は,家庭裁判所に相続しない旨,すなわち相続放棄の申述をする必要があります(ただし,期間制限があります。)。
当事務所では,相続放棄に関する一般的なご説明のみならず,相続放棄するべきかどうかについても,具体的なお話をお聞きした上でアドバイスいたします。
遺言書作成
<相談例>
・子供たちが遺産分割で争わないように,遺言書を作成しておきたい。
・自分が亡くなったら,お世話になったあの人に自分の財産を譲りたい。
遺言書を作成し,被相続人の意思を残すことで,遺産分割の諸手続が円滑に行われ,相続人間の争いを避けられることがあります。また,本来,自分の財産は自由に処分できるので,その処分方法について意思を明確にしておくことで,死後において,自己の思いを実現させることもできます。
当事務所では,どのような形(自筆証書遺言,公正証書遺言など)で遺言書を作成した方がよいのか,どのような言葉で残した方がよいのかなどについてアドバイスし,被相続人の方の意思を反映させた遺言書の作成をお手伝いいたします。
・子供たちが遺産分割で争わないように,遺言書を作成しておきたい。
・自分が亡くなったら,お世話になったあの人に自分の財産を譲りたい。
遺言書を作成し,被相続人の意思を残すことで,遺産分割の諸手続が円滑に行われ,相続人間の争いを避けられることがあります。また,本来,自分の財産は自由に処分できるので,その処分方法について意思を明確にしておくことで,死後において,自己の思いを実現させることもできます。
当事務所では,どのような形(自筆証書遺言,公正証書遺言など)で遺言書を作成した方がよいのか,どのような言葉で残した方がよいのかなどについてアドバイスし,被相続人の方の意思を反映させた遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言の執行
<相談例>
・自分が亡くなったときに遺言の内容を実現してもらいたい。
当事務所では,遺言書の作成とともに,遺言執行者に関するご依頼をいただければ,遺言執行者として遺言に基づく権利の移転,これに関連した必要な事務を行います。
・自分が亡くなったときに遺言の内容を実現してもらいたい。
当事務所では,遺言書の作成とともに,遺言執行者に関するご依頼をいただければ,遺言執行者として遺言に基づく権利の移転,これに関連した必要な事務を行います。
遺留分減殺請求
<相談例>
・特定の者が遺産のすべてを相続するという遺言書が作成されると,他の法定相続人は何も相続できないのか。
法律上,一定の相続人には,相続に際し,相続財産の一定割合を取得することが保障されています(遺留分,民法第1028条)。そのため,被相続人の生前の贈与又は遺贈によって,この遺留分が侵害された場合には,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分の侵害の限度で取り戻しを求めることができます(この取り戻す権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。)。
当事務所では,遺留分の侵害があるのかどうかの計算を行い,ご依頼があれば,弁護士が代理人となって遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺請求を行います。
・特定の者が遺産のすべてを相続するという遺言書が作成されると,他の法定相続人は何も相続できないのか。
法律上,一定の相続人には,相続に際し,相続財産の一定割合を取得することが保障されています(遺留分,民法第1028条)。そのため,被相続人の生前の贈与又は遺贈によって,この遺留分が侵害された場合には,贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分の侵害の限度で取り戻しを求めることができます(この取り戻す権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。)。
当事務所では,遺留分の侵害があるのかどうかの計算を行い,ご依頼があれば,弁護士が代理人となって遺留分を侵害している者に対して遺留分減殺請求を行います。
②離婚関係
親権者,養育費
<相談例>
・相手が子の親権を譲らず,離婚に関する話し合いが進まない。
・養育費をいくらにするかで争っている。
・相手が約束した養育費を支払ってくれない。
・以前に決めた養育費の額が支払えなくなったので減額したい。
離婚しようとするご夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合,お子さんの親権者となる親をいずれかに決めなければ,離婚することはできません(親権者の指定)。そのため,親権者の指定について夫婦間で争いになり,話し合いで合意ができないと,離婚調停手続や離婚訴訟の中で解決を図る必要が出てきます。しかし,離婚調停や離婚訴訟になった場合,自分が親権を取れるのか不安になってしまい,結果として,離婚に踏み切れないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
また,親権者の指定に関して互いに合意ができた場合,お子さんを引き取って監護することになる親は,他方の親に対し,お子さん監護に必要な費用(養育費)を求めることができます。ただ,養育費をいくらとするのか,相手が約束通りに支払わない場合にどうするかなどで争いになり,離婚手続きを進められないというケースもあります。
当事務所では,このような親権者の指定に関することや養育費についてのお悩みに対してアドバイスを行い,また、弁護士が代理人となって,相手方との交渉,請求等を行います。
・相手が子の親権を譲らず,離婚に関する話し合いが進まない。
・養育費をいくらにするかで争っている。
・相手が約束した養育費を支払ってくれない。
・以前に決めた養育費の額が支払えなくなったので減額したい。
離婚しようとするご夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合,お子さんの親権者となる親をいずれかに決めなければ,離婚することはできません(親権者の指定)。そのため,親権者の指定について夫婦間で争いになり,話し合いで合意ができないと,離婚調停手続や離婚訴訟の中で解決を図る必要が出てきます。しかし,離婚調停や離婚訴訟になった場合,自分が親権を取れるのか不安になってしまい,結果として,離婚に踏み切れないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
また,親権者の指定に関して互いに合意ができた場合,お子さんを引き取って監護することになる親は,他方の親に対し,お子さん監護に必要な費用(養育費)を求めることができます。ただ,養育費をいくらとするのか,相手が約束通りに支払わない場合にどうするかなどで争いになり,離婚手続きを進められないというケースもあります。
当事務所では,このような親権者の指定に関することや養育費についてのお悩みに対してアドバイスを行い,また、弁護士が代理人となって,相手方との交渉,請求等を行います。
財産分与
<相談例>
・相手が財産を開示せず,離婚に伴う財産の分配方法が決まらない。
・離婚するにあたり,婚姻中に購入した不動産の住宅ローンをどちらが支払っていくかで争いとなっている。
婚姻後に夫婦で築きあげた財産を離婚にあたって精算することを「財産分与」といいますが,離婚するにあたり,自分名義と相手名義の預金をどのように分けるか,婚姻中に購入した住宅をどちらが引き取るのか,どちらが住宅ローンを負担していくのかなどで争いとなってしまうことはよくあることです。
当事務所では,離婚に伴う財産の扱いについて,離婚後の将来のことも踏まえて,どのように考えればよいのかをアドバイスいたします。
・相手が財産を開示せず,離婚に伴う財産の分配方法が決まらない。
・離婚するにあたり,婚姻中に購入した不動産の住宅ローンをどちらが支払っていくかで争いとなっている。
婚姻後に夫婦で築きあげた財産を離婚にあたって精算することを「財産分与」といいますが,離婚するにあたり,自分名義と相手名義の預金をどのように分けるか,婚姻中に購入した住宅をどちらが引き取るのか,どちらが住宅ローンを負担していくのかなどで争いとなってしまうことはよくあることです。
当事務所では,離婚に伴う財産の扱いについて,離婚後の将来のことも踏まえて,どのように考えればよいのかをアドバイスいたします。
慰謝料
<相談例>
・相手の浮気(不貞)が発覚したことで離婚となったので慰謝料を請求したい。
・慰謝料の支払いについて決めたのに相手が支払わないので,これを支払わせたい。
離婚における慰謝料がいくらになるのかは,ケースバイケースであるため,一概には言えず,また仮に金額が確定したとしても,実際に相手から回収できるかは別に検討しなければなりません。
当事務所では,離婚することになった原因についてのお話をお聞きした上で,慰謝料として請求できる見込み,その金額や慰謝料の回収可能性についてアドバイスし,離婚についてのご依頼をいただいた際には,離婚請求とともに,相手に対して慰謝料も請求いたします。
・相手の浮気(不貞)が発覚したことで離婚となったので慰謝料を請求したい。
・慰謝料の支払いについて決めたのに相手が支払わないので,これを支払わせたい。
離婚における慰謝料がいくらになるのかは,ケースバイケースであるため,一概には言えず,また仮に金額が確定したとしても,実際に相手から回収できるかは別に検討しなければなりません。
当事務所では,離婚することになった原因についてのお話をお聞きした上で,慰謝料として請求できる見込み,その金額や慰謝料の回収可能性についてアドバイスし,離婚についてのご依頼をいただいた際には,離婚請求とともに,相手に対して慰謝料も請求いたします。
面会交流(面接交渉)
<相談例>
・離婚して,子供の親権を相手に渡したら,子供に会わせてくれなくなった。
・面会させることが子供にとって悪影響と思われる場合でも会わせないといけないのか悩んでいる。
ご夫婦(お子さんからすれば両親)が離婚したとしても,親子関係が消滅するわけではありません。お子さんの成長には,離れて暮らす親御さんとのコミュニケーションが重要になることもあります。
しかし,一方で,お子さんと面会させることが,かえってお子さんの精神的な成長を阻害しかねないケースもあります。いかなる場合に面会が認められるべきか,面会が認められるべきであるとして,その手段としてはどのような手続きを踏むべきなのか,一方,面会を制限させる方法はないのかなど,お子さんに関する問題は難しいものです。
当事務所では,弁護士が詳しい状況をお聞きし,お子さんにとって最良な結論を一緒に考えていきます。
・離婚して,子供の親権を相手に渡したら,子供に会わせてくれなくなった。
・面会させることが子供にとって悪影響と思われる場合でも会わせないといけないのか悩んでいる。
ご夫婦(お子さんからすれば両親)が離婚したとしても,親子関係が消滅するわけではありません。お子さんの成長には,離れて暮らす親御さんとのコミュニケーションが重要になることもあります。
しかし,一方で,お子さんと面会させることが,かえってお子さんの精神的な成長を阻害しかねないケースもあります。いかなる場合に面会が認められるべきか,面会が認められるべきであるとして,その手段としてはどのような手続きを踏むべきなのか,一方,面会を制限させる方法はないのかなど,お子さんに関する問題は難しいものです。
当事務所では,弁護士が詳しい状況をお聞きし,お子さんにとって最良な結論を一緒に考えていきます。
③成年後見等
成年後見人・保佐人・補助人
成年後見制度とは,例えば認知症によって判断能力を欠いたり,不十分な常況にある人(本人)に代わって,本人の財産を管理したり,生活上の諸手続を行う者を選任する制度のことをいい,本人の判断能力の差により,3つの手続き(成年後見人,保佐人,補助人)が用意されています。近時,高齢者の増加により,介護を必要とする方が増えていますが,家族であっても法律上の代理権が付与されない限り,本人に代わって法律行為をすることができないので,介護をしていく上で支障をきたすことがあります。
当事務所では,後見制度を利用する際に必要な諸手続についてアドバイスし,あるいは後見申立てに関する申立書の作成を行います。また,事情によっては,後見人候補者として申立てをし,裁判所から後見人への選任が認められたら,以後,ご本人の財産管理をいたします。
当事務所では,後見制度を利用する際に必要な諸手続についてアドバイスし,あるいは後見申立てに関する申立書の作成を行います。また,事情によっては,後見人候補者として申立てをし,裁判所から後見人への選任が認められたら,以後,ご本人の財産管理をいたします。
④不動産トラブル
賃貸借
<相談例>
・賃借人が家賃を何ヵ月も滞納しているので,賃貸借契約を解除して賃借人を出て行かせたい。
・地代を周辺の相場に合わせたい。
不動産の賃貸借に関するトラブルの中にも様々なものがあり,貸主(賃貸人)側と借主(賃借人)側の立場によって,その相談内容や対処法も変わってきます。
例えば,賃貸人の方が,家賃の滞納による建物の明渡しを求めたいというような事案の場合,まず借主に対し,話し合いによる解決の可能性を検討し,話し合いができないようであれば,裁判を視野に手続きを進めていくことになります。
当事務所では,賃貸人あるいは賃借人の立場に応じたアドバイスをし,ご依頼があれば代理人となって対処いたします。
・賃借人が家賃を何ヵ月も滞納しているので,賃貸借契約を解除して賃借人を出て行かせたい。
・地代を周辺の相場に合わせたい。
不動産の賃貸借に関するトラブルの中にも様々なものがあり,貸主(賃貸人)側と借主(賃借人)側の立場によって,その相談内容や対処法も変わってきます。
例えば,賃貸人の方が,家賃の滞納による建物の明渡しを求めたいというような事案の場合,まず借主に対し,話し合いによる解決の可能性を検討し,話し合いができないようであれば,裁判を視野に手続きを進めていくことになります。
当事務所では,賃貸人あるいは賃借人の立場に応じたアドバイスをし,ご依頼があれば代理人となって対処いたします。
境界,相隣関係
<相談例>
・隣人との間で土地の境界について争いとなっている。
・隣地に植わっている木の枝が,土地の境界を越えて伸びてきて困っている。
土地の境界の争いやそれに関連するトラブルは,多くは相手がご近所さんであることもあって,話し合いをもって解決を図ることが望ましいことですが,なかなか上手く解決できないことがあります。
当事務所では,どのような解決を図るべきかなどについてアドバイスし,ご依頼があれば,弁護士が代理人となって相手と交渉し,解決を目指します。
・隣人との間で土地の境界について争いとなっている。
・隣地に植わっている木の枝が,土地の境界を越えて伸びてきて困っている。
土地の境界の争いやそれに関連するトラブルは,多くは相手がご近所さんであることもあって,話し合いをもって解決を図ることが望ましいことですが,なかなか上手く解決できないことがあります。
当事務所では,どのような解決を図るべきかなどについてアドバイスし,ご依頼があれば,弁護士が代理人となって相手と交渉し,解決を目指します。
建築トラブル
<相談例>
・新築の家を購入したところ,雨漏りがして困っている。
・リフォームを頼んだら,見積もりと大幅に違う報酬金を請求されてしまった。
建築に関するトラブルは,日々の生活に直結するものであり,また高額になるケースが多いので,早急かつ慎重に解決を図りたいものです。
当事務所では,弁護士が詳しい事情をお聞きして,その対処法などについてアドバイスし,ご依頼があれば代理人となって対処いたします。
・新築の家を購入したところ,雨漏りがして困っている。
・リフォームを頼んだら,見積もりと大幅に違う報酬金を請求されてしまった。
建築に関するトラブルは,日々の生活に直結するものであり,また高額になるケースが多いので,早急かつ慎重に解決を図りたいものです。
当事務所では,弁護士が詳しい事情をお聞きして,その対処法などについてアドバイスし,ご依頼があれば代理人となって対処いたします。
⑤借金問題
自己破産
自己破産とは,収入や財産の中から債務の支払いができなくなってしまった場合に,裁判所に自己破産の申し立てを行って,債務者が保有している財産をお金に換えて債権者に平等に分配し,裁判所から免責の決定を得ると,債務のほとんどについて支払う責任を免除してもらうことができる制度です。裁判所から免責の許可決定が下りるかどうかは,借金を抱えるに至った事情や借入金の使途によって判断されます。
当事務所では,借金をするに至った事情などを詳しくお聞きして,自己破産の手続きがとれるかどうかを判断した上で,申し立てに必要となる書類を作成し,裁判所から免責の決定が得られるように,お手伝いいたします。
自己破産について,「自己破産をすると,貯金や家財道具を何もかもとられてしまうのではないか。」,「戸籍や住民票に自己破産をしたことが載ってしまうのではないか。」,「会社を解雇されてしまうのではないか。」等と不安になる方もいらっしゃると思います。こういった不安にも丁寧にお答えいたしますので,気軽にご相談ください。
当事務所では,借金をするに至った事情などを詳しくお聞きして,自己破産の手続きがとれるかどうかを判断した上で,申し立てに必要となる書類を作成し,裁判所から免責の決定が得られるように,お手伝いいたします。
自己破産について,「自己破産をすると,貯金や家財道具を何もかもとられてしまうのではないか。」,「戸籍や住民票に自己破産をしたことが載ってしまうのではないか。」,「会社を解雇されてしまうのではないか。」等と不安になる方もいらっしゃると思います。こういった不安にも丁寧にお答えいたしますので,気軽にご相談ください。
個人再生
個人再生とは,将来において継続的に収入を得られる見込みはあるけれども,多額の債務を抱えているために,約定どおりの返済ができなくなっているという場合に,裁判所での手続きを通じて債務を圧縮し,圧縮後の債務を原則3年間で分割して返済していくという制度です。この手続きに際して,住宅ローンについての特則(住宅資金特別条項)を付加すれば,住宅ローンはそれまで通りに返済しつつ,住宅ローン以外の債務を,上記のように圧縮して分割で返済していくということもできます。
当事務所にご依頼いただいた場合,債務や家計の状況,債務を抱えるに至った事情などを詳しくお聞きし,申立てに必要な書類を作成して裁判所に申し立てを行います。また,個人再生手続をとるにあたり,小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のどちらをとるべきなのか,債務をどのくらい圧縮することができるのか等,個人再生手続きの詳細については,ご相談時に弁護士からご説明いたしますので,ご不明な点がございましたら,お気軽にお尋ねください。
当事務所にご依頼いただいた場合,債務や家計の状況,債務を抱えるに至った事情などを詳しくお聞きし,申立てに必要な書類を作成して裁判所に申し立てを行います。また,個人再生手続をとるにあたり,小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続のどちらをとるべきなのか,債務をどのくらい圧縮することができるのか等,個人再生手続きの詳細については,ご相談時に弁護士からご説明いたしますので,ご不明な点がございましたら,お気軽にお尋ねください。
任意整理
任意整理とは,弁護士が代理人となって,各債権者との間で支払額及び支払方法について交渉し,和解契約を締結した上で,債務を弁済していくという債務整理の方法です。この方法によるべきかは,債務額,それぞれの収入見込みや生活状況などによって変わります。債務に関する整理の方法は人それぞれですので,まずはご相談下さい。
過払い金返還請求
テレビやラジオ,あるいは電車の広告などで大きな話題となったので,ご存じの方も多いかと思いますが,貸金業者や信販会社から金銭を借りた際の約定利息が,利息制限法で許される約定利率を超えて支払っていたような場合,同法に従って計算し直すと,借入金を払いすぎた(返済しすぎた)ことが判明することがあります。その払い過ぎた金員(すなわち,過払い金)の返還を求めることを「過払い金返還請求」といいます。
当事務所では,過払い金返還請求のご依頼をいただいた場合,まず,各業者に対して取引履歴の開示を請求し,その取引履歴をもとに利息制限法に基づく利息の引き直し計算をを行います。そして,計算の結果,過払い金が生じていた場合は,各業者に対し,過払い金の返還を求めて交渉し,必要があれば,過払い金返還請求訴訟を起こして,過払い金の返還を求めていきます。
当事務所では,過払い金返還請求のご依頼をいただいた場合,まず,各業者に対して取引履歴の開示を請求し,その取引履歴をもとに利息制限法に基づく利息の引き直し計算をを行います。そして,計算の結果,過払い金が生じていた場合は,各業者に対し,過払い金の返還を求めて交渉し,必要があれば,過払い金返還請求訴訟を起こして,過払い金の返還を求めていきます。
⑥損害賠償請求
不法に権利などを侵害され,損害を被った場合には,加害者に対し,損害賠償を請求することができます。交通事故は損害賠償請求の代表的なものの一つですが,これ以外にも実に様々なケースがあります。例えば,婚姻中のご夫婦の一方が浮気(不貞)をしたことが原因で離婚となった場合に,浮気をした配偶者だけでなく,浮気相手に対しても慰謝料を請求する場合がこれに該当します。
損害賠償請求をしようとお考えの方は,是非,ご相談ください。
損害賠償請求をしようとお考えの方は,是非,ご相談ください。
⑦刑事事件
ご自分もしくはご家族の方が刑事事件に関与してしまった場合,今後,どういう手続きになっていくのか,とても不安に感じることと思います。また,万一,警察に逮捕されて警察署等に留置されてしまったら,外部との連絡が制限されてしまうため,日常生活に大きな影響を受けることになります。
当事務所に刑事弁護のご依頼をいただいた場合,直ちに本人に面会に行き,必要に応じて,ご家族に現在の状況と今後の見通しなどのお話をし,被害者がいるケースであれば,必要に応じて示談交渉などを行います。そして,万一,刑事裁判になった場合には,ご本人の利益につながるよう,全力で弁護いたします。是非,当事務所にご相談ください。
当事務所に刑事弁護のご依頼をいただいた場合,直ちに本人に面会に行き,必要に応じて,ご家族に現在の状況と今後の見通しなどのお話をし,被害者がいるケースであれば,必要に応じて示談交渉などを行います。そして,万一,刑事裁判になった場合には,ご本人の利益につながるよう,全力で弁護いたします。是非,当事務所にご相談ください。
⑧その他
内容証明郵便の作成
内容証明郵便とは,いつ,どのような内容の文書を,誰から誰に差し出したのか,ということを郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる郵便のことをいいます。例えば,相手方に貸金の返還を求める催告をするにあたり,単なる手紙ではなく,きちんとした書面を送りたい,賃貸借契約を解除する前提として催告書を送りたい,というようなケースで利用されます。
内容証明郵便を作成したいが,自分ではうまく作成できないという方は,当事務所にご依頼いただければ,弁護士が詳しい事情をお伺いした上で,内容証明郵便の文章を作成し,郵便局で送付手続きを行います。また,必要に応じて相手との示談交渉も行います。
内容証明郵便を作成したいが,自分ではうまく作成できないという方は,当事務所にご依頼いただければ,弁護士が詳しい事情をお伺いした上で,内容証明郵便の文章を作成し,郵便局で送付手続きを行います。また,必要に応じて相手との示談交渉も行います。
契約書の作成
当事者間で,ある事項について合意した場合,後のトラブルを防止するために,合意した内容を書面にしておくことは,ビジネスの世界ではもちろん,日常生活の中でもありえることです。しかし,その際に,どのような文章(言葉)を書くべきなのか,悩まれる方も多いのではないでしょうか。
当事務所では,弁護士が、どのような内容の書面を作成したいのかについてお話をお聞きした上で,契約書等の書面を作成をいたします。是非,ご相談ください。
当事務所では,弁護士が、どのような内容の書面を作成したいのかについてお話をお聞きした上で,契約書等の書面を作成をいたします。是非,ご相談ください。